人が好き 歌が好き お酒が好き
ましてや絵描くことは…
絵をご覧になりながら どうぞ私と一緒に
心を遊ばせて下さい。
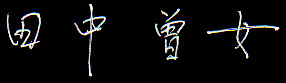
ましてや絵描くことは…
絵をご覧になりながら どうぞ私と一緒に
心を遊ばせて下さい。
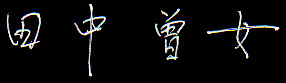
田中曽女さんが、生地の朝鮮の慶尚南道の普州から引き上げてきて、4歳から成育したのは、香川県高松近郊の仏生山というところである。今は、市内となって、その中南部に位置していて、琴平線にその名の駅のある町である。
30年ほど昔、一度通過した程度の知識しか私にはないが、法然寺という名刹があって、参詣者を集めている。この寺は、承久元年(1207)に、浄土宗の開祖法然上人が念仏停止の措置を受けて配流されて、その基礎を建立したと伝えられる。ここにある三仏堂は、涅槃堂と呼ばれているように、金色六丈の寝釈迦を中心に、死を悼む五十二類の姿の彩色木彫が並んでいて、絵画を立体化した独特の様式で名高く、京都嵯峨の立釈迦と並称されている。
曽女さんは、この寺や近くの平池で日がな一日、絵を描きながら、幼児を過ごしたそうで、その記憶が、恐らく、画家となってから形成する自分の画像の基礎にあるのではないか、と思われる。たしかに、ある時期からの彼女が描く画像には、どこか、仏教的な雰囲気が漂っている。それについては後で述べるとして、この時期の曽女さんは、どちらかというと、音楽に熱中していたようだが、それから10年後の彼女は、早くから好んでいたもう一つの芸術である絵画へと改めて眼を向けるようになって、1967年から、独学にして晩(?)学の絵画制作に打ち込む。
 年譜によると、この画家の作品発表は、78年の女流画家協会展からで、それと平行して、85年から現代美術家協会展への出品が始まって、すでに25年となる。今回の大規模な展覧会で、冒頭を飾るのは、「森の中から」と題される85-86年の連作であり、自然のなかにたたずむ少女という、多分に叙情的な絵画を当時描いていたことが分かるが、見方によれば、これを以って、彼女は前史に区切りを付けたと言ってよく、一人の画家として本格的な第一歩を踏み出すのは、これ以後である。
年譜によると、この画家の作品発表は、78年の女流画家協会展からで、それと平行して、85年から現代美術家協会展への出品が始まって、すでに25年となる。今回の大規模な展覧会で、冒頭を飾るのは、「森の中から」と題される85-86年の連作であり、自然のなかにたたずむ少女という、多分に叙情的な絵画を当時描いていたことが分かるが、見方によれば、これを以って、彼女は前史に区切りを付けたと言ってよく、一人の画家として本格的な第一歩を踏み出すのは、これ以後である。
それからの彼女はどんな絵を描くようになったかと見ると、意外なことに、前後関係のまったくない純然たる静物画である。その静物も、すべて枯れた花、葉と果実であり、描写の仕方も、極力感情を抑制して客観性に徹したものとなっている。それはそれとして特色ある作品となってはいるが、成否を別にして何よりも強く感じとれるのは、自分を一人の画家として鍛え上げようとする厳しさを自覚した作者の姿勢と技術である。この地道な制作を寡黙に推し進めていく途上に、80年代の終わりからの再度のより大きな様式の反転が現れる。
妖艶な女性像の復活である。しかし、それは前史のものとはおよそ様相を異にし、89年の5連作を見ると、少女はすでに成熟を遂げていて、一人の人間として、生、愛、苦悩、憂、祈といった明暗の諸相を経験した、精神の面での相当な屈折を示している。聞くところによると、愛する弟の突然の死から受けた強い衝撃からそれは生まれたという。
この沈痛な経験に基づいて、「人生」という問題が主要な主題として、この画家の絵画に位置するようになるのは、91年の「それぞれの旅立ち」以来である。左右に二分された画面の、一方では、男性群が「幽」の深い森へと向かい、他方では、全裸の女性群が「明」の雲霧の中を飛翔する━━その境界の丘の上に立って、孤独な女性が、後ろ向きに座す影のごとき人物を傍らにして、虚空を仰いで瞑目しているのこの悲喜こもごもの心象風景は、今や、一人の画家の自立を認識させるに十分な画期的な力作だった。
これに続く作品では、黒の面積がいちじるしく増大し、漆黒の背景から浮かび出て、悶え、浮遊し、逆転し、俯つ伏す白い肌あるいは金の輪郭の女性、そして夢魔のように翼を広げる芥子の白花が描き継がれる。そして、前者は時に黒に転じ、後者は逆転して白のなかから艶やかな赤を浮き立たせ、また、白い肌が白の花冠に沈む情景も現れ、それぞれ入り交じりもして、独特な画家の変奏が続く。一見していずれも幻想的ではあるが、しかし、この種の絵画で稀薄になりがちな、一種強烈な衝撃が跳ね返ってくるのは、不思議である。
 1993年以降の大きな花をモティーフにした一連の作品を、一つのシンフォニーのように眼で追っていくと、おのずから、主題として表出するのは、女性自身である。彼女は花心あるいは花冠に置かれて、さまざまな姿態で描かれてはいるが、その根本的なイメージは、うずくまり、横たわる胎児から少女に至る遠い過去の形姿と二重写しになっている自分のように見える。それらは、スーヴニール(回想)の形で叙述されているのだが、しかし、けっして追憶に終わることなく、そこから現代の自分に跳ね返って来る感情を描くことを忘れていない。いわば「人生」を観照する自分自身の感慨を、作者は、それらの純白や真紅の花に託して、時に仏画を思わせる深々とした幽明な空間のなかに描き出す。
1993年以降の大きな花をモティーフにした一連の作品を、一つのシンフォニーのように眼で追っていくと、おのずから、主題として表出するのは、女性自身である。彼女は花心あるいは花冠に置かれて、さまざまな姿態で描かれてはいるが、その根本的なイメージは、うずくまり、横たわる胎児から少女に至る遠い過去の形姿と二重写しになっている自分のように見える。それらは、スーヴニール(回想)の形で叙述されているのだが、しかし、けっして追憶に終わることなく、そこから現代の自分に跳ね返って来る感情を描くことを忘れていない。いわば「人生」を観照する自分自身の感慨を、作者は、それらの純白や真紅の花に託して、時に仏画を思わせる深々とした幽明な空間のなかに描き出す。
他の多くの画家とは異なり、きらきらする外光にほとんど反応せず、曖昧な混色を避けて、白と黒の対比に徹底し、それに鮮烈な赤を加えて一切を表現するこの画家は、小品に佳作はあるとしても、大作に力量を発揮する素質を具えている。彼女独特のこの絵画的なシンフォニーが、この先どのように展開して、どんな大きな曲を作り上げることになるか。もっぱらこのことに、私の思いは馳せる。
30年ほど昔、一度通過した程度の知識しか私にはないが、法然寺という名刹があって、参詣者を集めている。この寺は、承久元年(1207)に、浄土宗の開祖法然上人が念仏停止の措置を受けて配流されて、その基礎を建立したと伝えられる。ここにある三仏堂は、涅槃堂と呼ばれているように、金色六丈の寝釈迦を中心に、死を悼む五十二類の姿の彩色木彫が並んでいて、絵画を立体化した独特の様式で名高く、京都嵯峨の立釈迦と並称されている。
曽女さんは、この寺や近くの平池で日がな一日、絵を描きながら、幼児を過ごしたそうで、その記憶が、恐らく、画家となってから形成する自分の画像の基礎にあるのではないか、と思われる。たしかに、ある時期からの彼女が描く画像には、どこか、仏教的な雰囲気が漂っている。それについては後で述べるとして、この時期の曽女さんは、どちらかというと、音楽に熱中していたようだが、それから10年後の彼女は、早くから好んでいたもう一つの芸術である絵画へと改めて眼を向けるようになって、1967年から、独学にして晩(?)学の絵画制作に打ち込む。
 年譜によると、この画家の作品発表は、78年の女流画家協会展からで、それと平行して、85年から現代美術家協会展への出品が始まって、すでに25年となる。今回の大規模な展覧会で、冒頭を飾るのは、「森の中から」と題される85-86年の連作であり、自然のなかにたたずむ少女という、多分に叙情的な絵画を当時描いていたことが分かるが、見方によれば、これを以って、彼女は前史に区切りを付けたと言ってよく、一人の画家として本格的な第一歩を踏み出すのは、これ以後である。
年譜によると、この画家の作品発表は、78年の女流画家協会展からで、それと平行して、85年から現代美術家協会展への出品が始まって、すでに25年となる。今回の大規模な展覧会で、冒頭を飾るのは、「森の中から」と題される85-86年の連作であり、自然のなかにたたずむ少女という、多分に叙情的な絵画を当時描いていたことが分かるが、見方によれば、これを以って、彼女は前史に区切りを付けたと言ってよく、一人の画家として本格的な第一歩を踏み出すのは、これ以後である。それからの彼女はどんな絵を描くようになったかと見ると、意外なことに、前後関係のまったくない純然たる静物画である。その静物も、すべて枯れた花、葉と果実であり、描写の仕方も、極力感情を抑制して客観性に徹したものとなっている。それはそれとして特色ある作品となってはいるが、成否を別にして何よりも強く感じとれるのは、自分を一人の画家として鍛え上げようとする厳しさを自覚した作者の姿勢と技術である。この地道な制作を寡黙に推し進めていく途上に、80年代の終わりからの再度のより大きな様式の反転が現れる。
妖艶な女性像の復活である。しかし、それは前史のものとはおよそ様相を異にし、89年の5連作を見ると、少女はすでに成熟を遂げていて、一人の人間として、生、愛、苦悩、憂、祈といった明暗の諸相を経験した、精神の面での相当な屈折を示している。聞くところによると、愛する弟の突然の死から受けた強い衝撃からそれは生まれたという。
この沈痛な経験に基づいて、「人生」という問題が主要な主題として、この画家の絵画に位置するようになるのは、91年の「それぞれの旅立ち」以来である。左右に二分された画面の、一方では、男性群が「幽」の深い森へと向かい、他方では、全裸の女性群が「明」の雲霧の中を飛翔する━━その境界の丘の上に立って、孤独な女性が、後ろ向きに座す影のごとき人物を傍らにして、虚空を仰いで瞑目しているのこの悲喜こもごもの心象風景は、今や、一人の画家の自立を認識させるに十分な画期的な力作だった。
これに続く作品では、黒の面積がいちじるしく増大し、漆黒の背景から浮かび出て、悶え、浮遊し、逆転し、俯つ伏す白い肌あるいは金の輪郭の女性、そして夢魔のように翼を広げる芥子の白花が描き継がれる。そして、前者は時に黒に転じ、後者は逆転して白のなかから艶やかな赤を浮き立たせ、また、白い肌が白の花冠に沈む情景も現れ、それぞれ入り交じりもして、独特な画家の変奏が続く。一見していずれも幻想的ではあるが、しかし、この種の絵画で稀薄になりがちな、一種強烈な衝撃が跳ね返ってくるのは、不思議である。
 1993年以降の大きな花をモティーフにした一連の作品を、一つのシンフォニーのように眼で追っていくと、おのずから、主題として表出するのは、女性自身である。彼女は花心あるいは花冠に置かれて、さまざまな姿態で描かれてはいるが、その根本的なイメージは、うずくまり、横たわる胎児から少女に至る遠い過去の形姿と二重写しになっている自分のように見える。それらは、スーヴニール(回想)の形で叙述されているのだが、しかし、けっして追憶に終わることなく、そこから現代の自分に跳ね返って来る感情を描くことを忘れていない。いわば「人生」を観照する自分自身の感慨を、作者は、それらの純白や真紅の花に託して、時に仏画を思わせる深々とした幽明な空間のなかに描き出す。
1993年以降の大きな花をモティーフにした一連の作品を、一つのシンフォニーのように眼で追っていくと、おのずから、主題として表出するのは、女性自身である。彼女は花心あるいは花冠に置かれて、さまざまな姿態で描かれてはいるが、その根本的なイメージは、うずくまり、横たわる胎児から少女に至る遠い過去の形姿と二重写しになっている自分のように見える。それらは、スーヴニール(回想)の形で叙述されているのだが、しかし、けっして追憶に終わることなく、そこから現代の自分に跳ね返って来る感情を描くことを忘れていない。いわば「人生」を観照する自分自身の感慨を、作者は、それらの純白や真紅の花に託して、時に仏画を思わせる深々とした幽明な空間のなかに描き出す。他の多くの画家とは異なり、きらきらする外光にほとんど反応せず、曖昧な混色を避けて、白と黒の対比に徹底し、それに鮮烈な赤を加えて一切を表現するこの画家は、小品に佳作はあるとしても、大作に力量を発揮する素質を具えている。彼女独特のこの絵画的なシンフォニーが、この先どのように展開して、どんな大きな曲を作り上げることになるか。もっぱらこのことに、私の思いは馳せる。
